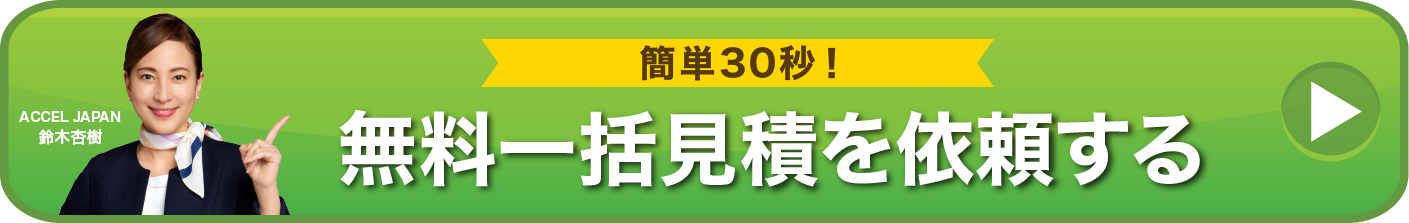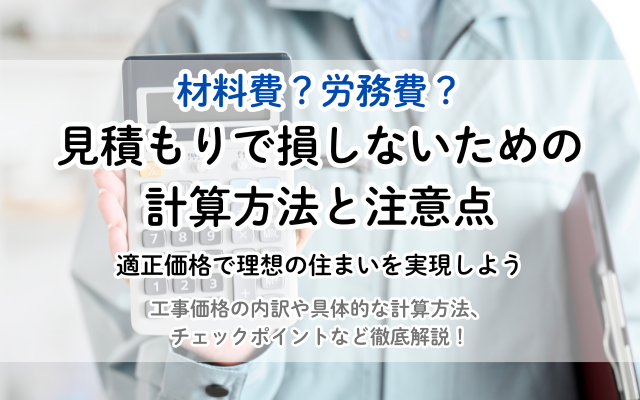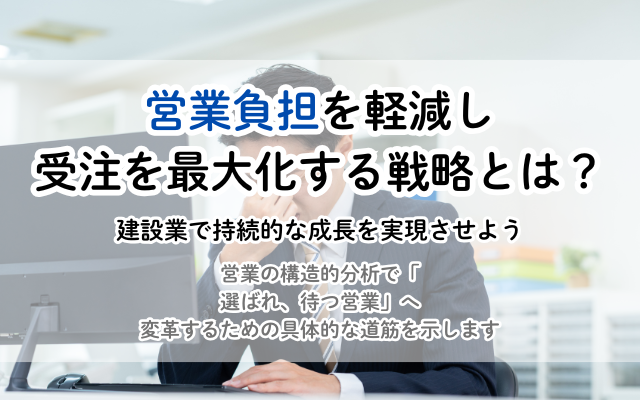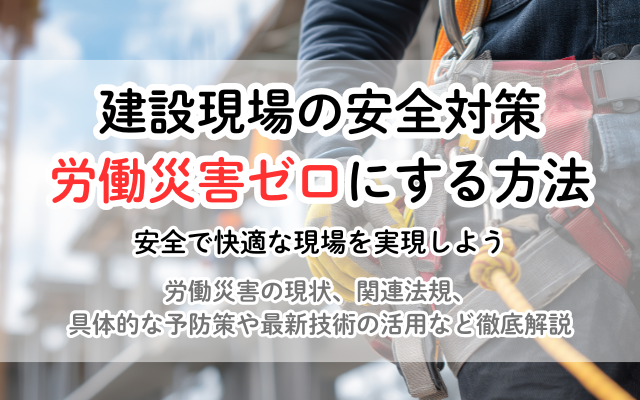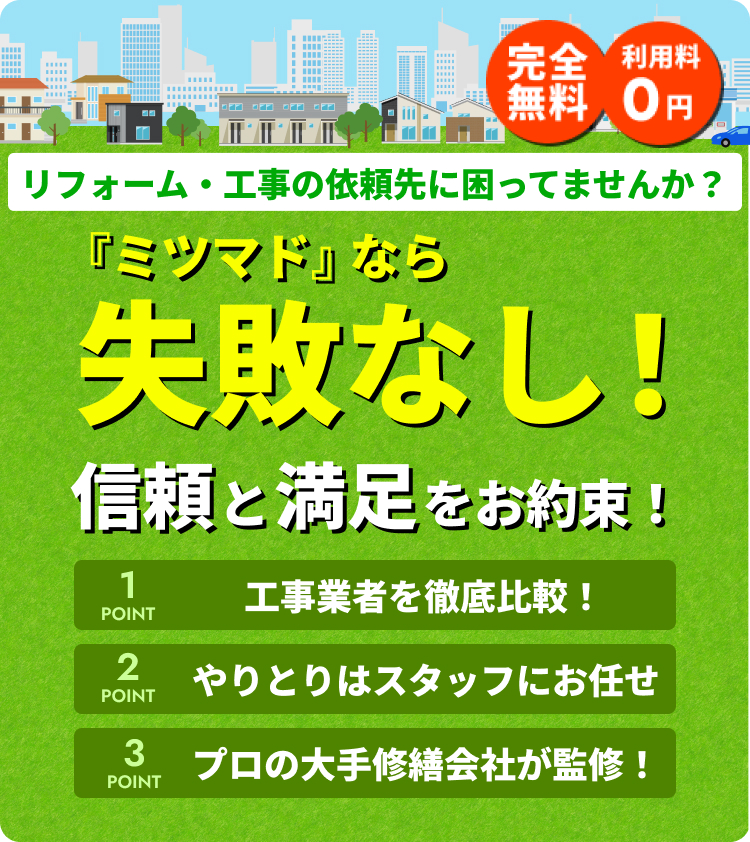1. 増築とは?
増築を検討し始めると、「増築」の他に「改築」という似たような言葉が登場して戸惑ってしまいます。以下では増築と改築の違いや、増築にかかる費用など、増築の基礎知識について解説します。
1-1. 増築の定義
「増築」とは、既存の建物に構造を追加して建物の床面積を増やす工事のことです。
たとえば以下のような工事が増築に当たります。
- 平屋の家に2階部分を付け加える
- リビングの隣に新しい部屋を作る
- 敷地内に母屋と別に離れを建てる
一般的に増築ができるのは一戸建ての住宅です。マンションは居住スペースに新たに床面積を増やすための空きスペースを確保できないため、物理的に増築ができません。
増築は建物の一部のみを取り壊すため、建物を取り壊して立て直す「建て替え」よりも費用を抑えられ、工事の期間を短縮できます。
建て替えや改築と比べると、その家に住みながら工事できるケースが多いのも特徴です。仮住まいの物件を不動産屋で探したり、その間の家賃を払ったりする必要がありません。
一方で、床面積が増えて固定資産税が増えてしまう点がデメリットです。既存部分と増築部分の耐震性や耐久性が異なってしまうこと、外観がちぐはぐになりがちなことにも注意して、しっかりリフォーム会社と相談をしましょう。
増築の際には、耐震基準に適しているか、建築基準法や地域の条例に違反していないかなどを確認する必要があります。
また法令や都市計画などの改正のため、現在の建築基準法に準拠しなくなっている建物(既存不適格建築物)を増築する場合には、不適格となっている部分を改修して現在の建築基準法に適合させるのが基本です。
1-2. 改築との違い
増築と改築の最大の違いは「床面積が増えるかどうか」です。
「改築」とは、家の一部または全部を壊し、新しいものに修理する工事を指します。その際、床面積が変更してしまう工事は改築には当たりません。
壊す前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えるのが改築の特徴です。
たとえば2部屋をつなげて1部屋にする、和室から洋室に変更する、などが改築工事です。
1-3. 増築にかかる費用の内訳
増築にかかる諸費用には、大きく分けると次の3つがあります。
- 材料費
- 工事費
- 確認申請費用
材料費は、増築部分の構造材や内装材、設備費用などにかかる費用です。
工事費は、材料以外の工事にかかる費用です。大工工事、電気工事、水道工事などの労務費や、足場工事、機械機器などの費用も含みます。工期が長くなればその分、費用がかかります。
確認申請費用は、確認申請で必要な手数料です。費用は自治体によって異なるため事前に確認が必要です。
確認申請とは、増築によって建築物が法律や条例に違反していないかを自治体の職員や指定確認検査機関に確認してもらう手続きを指します。
「確認申請」「中間検査」「完了検査」の3つの手続きがあり、それぞれで手数料が発生します。
確認申請が必要になるのは次の場合です。
- 10平方メートル以上の増築工事
- 防火地域、準防火地域の増築工事
防火地域や準防火地域は、都市計画法で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されているエリアです。
増築には高額になると数百万円の費用が必要です。そのため、自宅の増築にも住宅ローンを利用できます。他にも審査の手続きが簡単な、リフォーム専用のリフォームローンを利用できる金融機関があります。
新築と同じように、確定申告で所得税から一定額が控除される住宅ローン減税が適用される場合があるため、自分が該当するかどうか条件を確認しておきましょう。

2. 【構造別】増築にかかる費用の目安
増築にかかる費用は、建物の構造や増築する面積などによって変わります。以下より目安となる金額を紹介します。
2-1. 住宅構造別の増築費用目安
住宅の構造別で増築にかかる費用の相場は以下の通りです。
| 住宅構造 | 増築にかかる費用の相場 |
|---|---|
| 木造住宅 | 70万円~280万円 |
| 鉄骨住宅 | 100万円~400万円 |
| 2階の増築 | 120万円~480万円 |
増築にかかる費用は、住宅が木造か鉄骨かで大きく変わってきます。
また、増築して平屋を2階建てにする場合は、1階部分の増築よりも費用が高くなります。
耐震強度を高めるための耐震補強工事や、屋根の解体や作り直し、階段の増設などが必要になるためです。
さらに水まわり設備の有無や階段の位置などによっては、配管工事や住宅構造の補強工事が必要な場合があり追加の費用が必要です。
2-2. 面積別の増改築費用目安
面積別の増改築費用の目安は以下の通りです。
| 木造住宅 | 鉄骨住宅 | 2階部分の増築 | |
|---|---|---|---|
| 2坪 (4畳) | 140万円前後 | 200万円前後 | 240万円前後 |
| 3坪 (6畳) | 210万円前後 | 300万円前後 | 360万円前後 |
| 5坪 (10畳) | 350万円前後 | 500万円前後 | 600万円前後 |
増築部分の面積が増えるほど費用は増えます。
増築費用は坪単価で、木造住宅で70万円前後、鉄骨住宅で100万円前後です。2階の増築は、120万円前後を目安にしてください。
3. 【箇所別】増築にかかる費用の目安
増築の費用は、どこを増築するかによっても差が生じます。箇所別の費用目安は以下の通りです。
| 場所 | 増築費用の目安 |
|---|---|
| トイレ | 約70万円~200万円 |
| バスルーム | 約50万円~180万円 |
| キッチン | 約100万円~400万円 |
| リビング | 約200万円~300万円 |
| 和室 | 約200万円~300万円 |
| 洋室 | 約70万円~130万円 |
| ベランダ・バルコニー | 約50万円~94万円 |
| サンルーム | 約40万円~200万円 |
| ガレージ | 約100万円~300万円 |
| カーポート | 約20万円~70万円 |
| 地下室 | 約600万円~約1,000万円 |
水まわりの増築は、新しい設備の購入費や撤去した古い設備の処分費に加え配管工事が必要になるため、費用がかさんでしまいます。
地下室を増築する場合は、地下室そのものの工事のほかに、事前のボーリング調査や建物の基礎部分の補強費などが発生します。費用が高額になってしまうことを知っておきましょう。
4. 増築費用を抑えるポイント
増築の費用はできるだけ予算内に収めたいですよね。以下より費用を抑えるためのポイントをお伝えします。
4-1. 複数の業者に見積もりを依頼する
同じ工事内容でも依頼するリフォーム会社によってリフォーム費用が異なります。増築を検討するときには複数社から見積書をとりましょう(相見積)。
できるだけ同じ条件で相見積をとって比較すれば、増築工事の費用相場がわかり適正な価格帯も判断しやすくなります。
見積もりをとった後は、金額だけを比較するのではなく何の工事でいくらの費用が必要なのか、工事後の補償はどうなっているのかなど詳細な部分まで確認しましょう。
4-2. 材料費を抑える
増築にかかる費用を抑えたい場合には材料費にも注目してください。
増築にかかる費用のうち、幅があるものが材料費です。建材や備品には豊富な種類があり、グレードを下げることでコストダウンが可能です。
施工会社に前もって決めておいた予算を伝えておき、予算の範囲で収まるように相談しましょう。
4-3. 増改築を検討している箇所はまとめて工事を行う
増改築を数回に分けて実施すると、解体作業や足場、養生などの費用がその都度かかります。全体の費用を抑えたいなら、まとめて工事を行えるかどうかを検討してみてください。
水まわりの設備などは、セットで購入すると単体で注文するときよりも割引される場合があります。
4-4. 水まわりの増設は配管距離を確認する
2階にトイレを増設する、離れに風呂を作るなど、水まわりの増設をするときには配管の距離を確認しましょう。
配管の位置や移動距離によって費用が大きく変わります。現状の配管から離れれば離れるほど、配管の延長や移動工事が必要になり費用がかさんでしまいます。
できるだけ配管の延長が短く済んだり、移動工事が必要のない増設工事となるよう計画をしましょう。
4-5. 補助金や助成金を活用する
増築工事にも、国や地方自治体の補助金や助成金、減税制度を利用できる場合があります。施工内容や地域、対象者によっても異なるため自治体の窓口に問い合わせてみましょう。
2024年現在、増築に活用できる補助金・助成金制度の事例として、次のようなものがあります。
・介護保険における住宅改修
介護保険における住宅改修は、介護が必要となった方が自宅で安全に暮らせるよう、住宅改修を行うための費用の一部を助成する国の制度です。
手すりの取付や段差の解消、扉から引き戸への交換などの改修に対して、18万円を上限として助成します。
参考:介護保険における住宅改修(厚生労働省)
・既存住宅における断熱リフォーム支援事業
2023年から始まった環境省の補助金・助成金制度の最新版が、「先進的窓リノベ2024事業」です。断熱窓へのリフォームを促進して既存住宅の省エネ化を促し、二酸化炭素の排出削減を進める目的があります。
既存の住宅を所有する全世帯で、断熱性能が高い窓や玄関ドアへのリフォームが補助金の対象です。
補助金の上限は1戸あたり200万円となっています。
参考:先進的窓リノベ2024事業(環境省)
・地方自治体の補助金
各自治体が独自に実施している補助金制度にも注目しましょう。以下より令和5年度の事例を2つ紹介します。
島根県の「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業」では、子どもと同居する世帯や60歳以上の方、あるいは身体障がいのある方が居住する住宅のリフォームを対象にした補助金です。1戸あたり上限25万円を助成しています。
大阪市の「民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度」は、耐震化工事に要する費用の一部を補助する制度です。
参考:
しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業(島根県)
民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度(大阪市)
その他、地域によってさまざまな制度がありますので、お住まいの自治体のホームページなどで最新情報を確認してください。
5. 増築にかかる費用を知って満足のいく増築を
増築にかかる費用は坪単価で、木造住宅の場合は70万円前後、鉄骨住宅での場合は100万円前後です。
さらに、増築の箇所や面積などによっても変わってきます。ローンや補助金を利用しながら、満足のいく増築をして快適な生活を手に入れましょう。
増築でお悩みの際は、あらゆる建物の工事・リフォームの一括見積もりが可能な『ミツマド』の利用がおすすめです。
厳しい審査基準をクリアした安心・信頼できる優良企業・職人をご紹介しますので、安心して業者選定を行えます。
また、専門スタッフが安心して工事を進められるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。