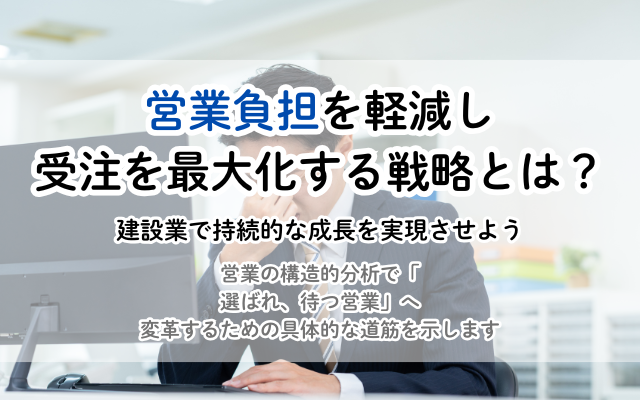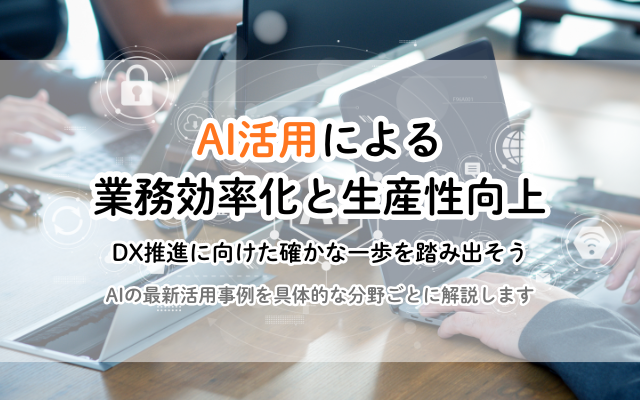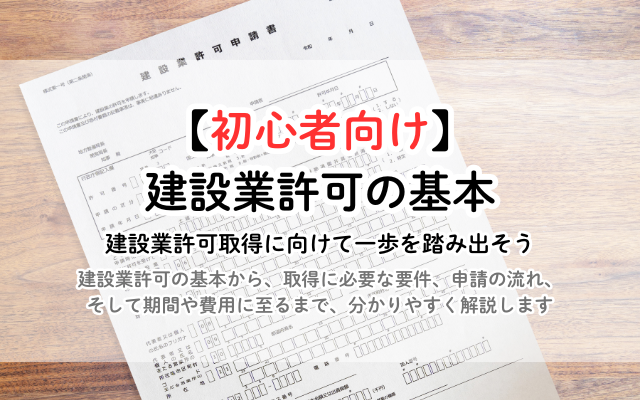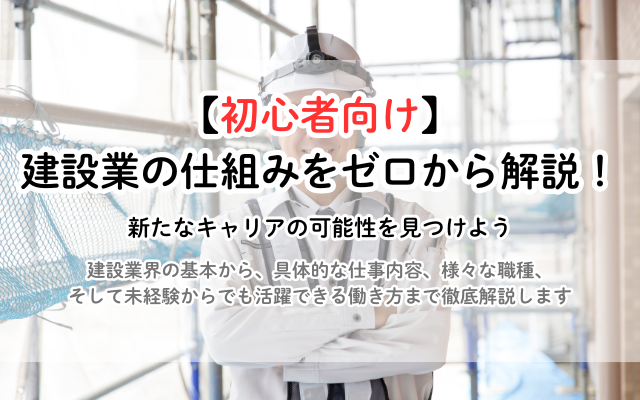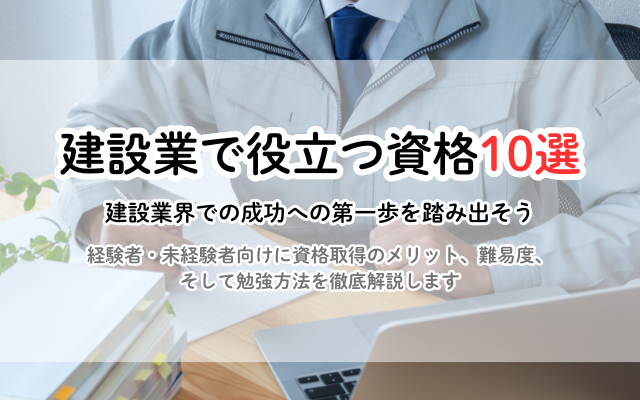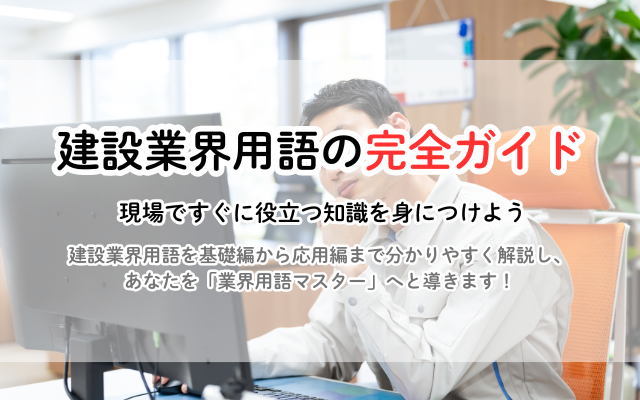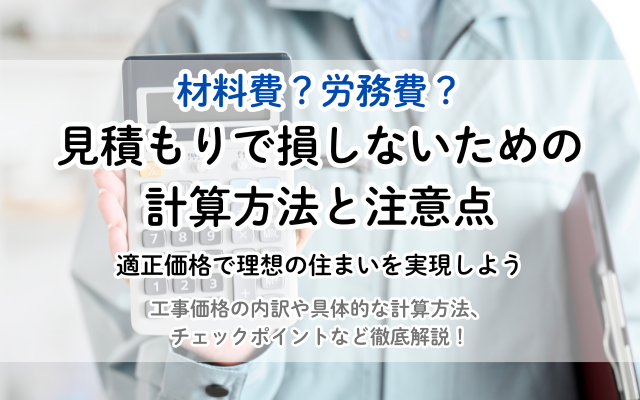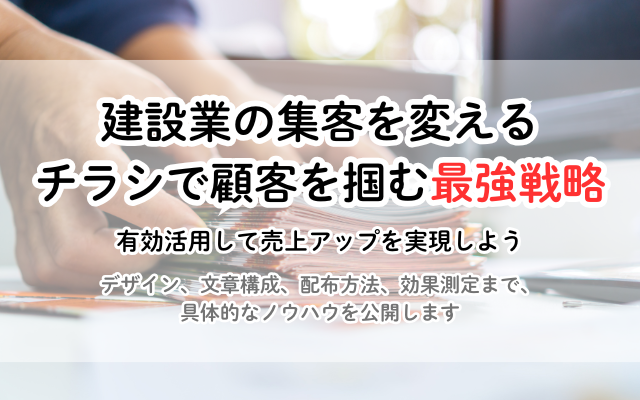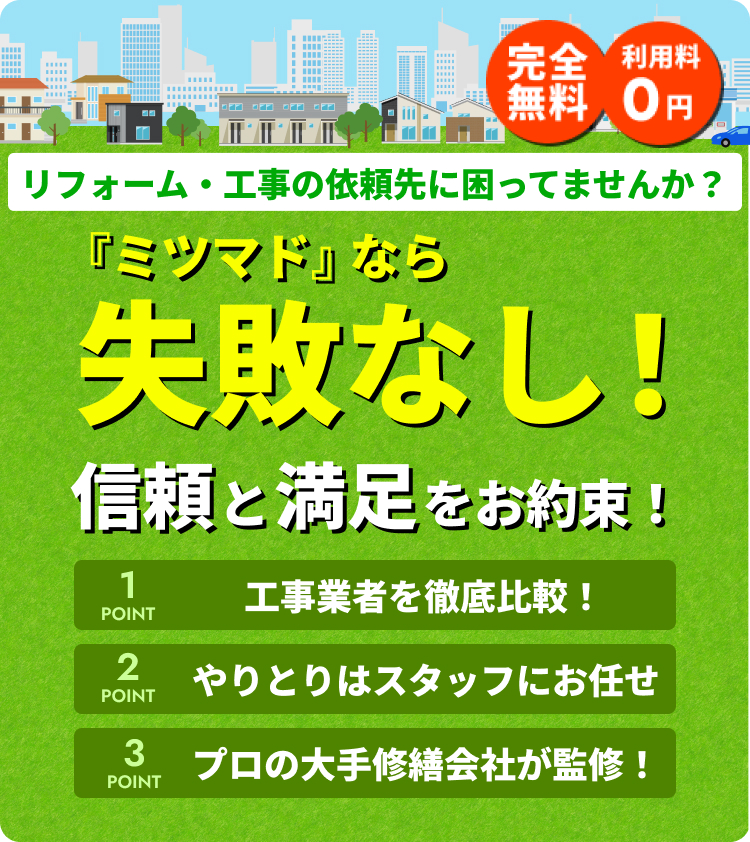1. 建設業における「営業負担」の現実
1-1. 深刻化する人手不足と非効率な営業活動がもたらす影響
建設業界が直面する最大の課題の一つ、それは人手不足です。技術者や技能労働者の高齢化が進む一方で、若年層の入職率は十分ではありません。この問題は、単に「現場の担い手が足りない」というだけではなく、間接部門である「営業」の役割と負担を根本から変質させています。
本来、営業職は依頼主と現場の間に立ち、会社の技術力と信頼を背景に、顧客の理想を叶える「重要な先導役」であるべきです。しかし現状では、多くの建設業の営業担当者が、直接的な利益に結びつきにくい非効率な活動に貴重な時間を浪費してしまっています。
- 非生産的な移動時間: 顧客訪問や現場調査のための移動は、デスクワークや提案資料作成を中断させます。特に広範囲をカバーする場合、一日のうちで数時間が運転や公共交通機関の待ち時間に費やされています。
- 不確実なアポイントメント: 「顔見知り」の関係を維持するための定期的な訪問や、アポイントメントが確定していない飛び込み訪問は、担当者が不在の場合も多く考えられます。
- 現場と営業の間の「伝書鳩」: 依頼主からの技術的な質問に対し、すぐに答えられず、一度持ち帰って現場や設計担当者に確認し、改めて返答することがあります。この往復のコミュニケーションロスが、営業のリードタイム(期間)を不必要に伸ばしています。

1-2. 変化する市場環境:紹介依存からの脱却と競争の激化
かつての建設業界では、「地元の信用」や「過去の実績」に基づく紹介案件が、安定した受注の柱でした。しかし、顧客の意識や情報収集の方法が変化し、状況は一変しています。
インターネットの普及により、顧客は契約前に複数の施工事例、技術、価格を簡単に比較できるようになりました。これは、地域の工務店であっても、都市部の専門業者とオンライン上で比較されることを意味します。
この結果、営業担当者は「顔なじみだから」という理由だけで受注を得ることは難しくなり、データと根拠に基づいた「競争力のある提案」を常に求められるようになりました。この要求に応えるためには、膨大な調査と提案資料の準備が必要となり、これもまた大きな負担となっています。
また、最も営業担当者を疲弊させるのが、相見積もりの増加です。受注に至らないにもかかわらず、詳細な設計図の読み込み、資材価格の変動チェック、緻密な工数計算を要求される相見積もりへの対応は、営業リソースを食いつぶす最大の要因です。特に、価格のみを比較検討する依頼主への対応は、技術力や提案の価値が評価されにくく、営業担当者のモチベーションを低下させ、ひいては見積もりミスのリスクも高めます。
2. なぜ建設業の営業は「重労働」なのか?
2-1. 既存の営業フローの課題
建設業の営業担当者が抱える負担の根源は、確立されてしまったアナログで非効率な営業プロセスにあります。デジタル化が進む現代においても、依然として紙・電話・足による訪問に依存しがちです。また、建設プロジェクトは一般的に意思決定のプロセスが非常に長く複雑な為、契約に至るまでの負担が大きくなっています。
- 検討期間の長期化: 依頼主は多額の投資となるため、計画立案から業者の選定、契約に至るまでに数ヶ月、時には数年を要します。
- 継続的な人的フォロー: 営業担当者は、この長い期間、定期的な状況確認の電話や訪問、進捗報告のための資料作成など、継続的な人的フォローを強いられます。このフォローアップ活動自体に多くの時間を消費します。
- 情報共有の手間: 顧客から質問があるたびに、社内の設計、積算、現場監督など複数の部署に確認を取り、その情報を整理して顧客に伝えるという、仲介(伝書鳩)的な役割が避けられず、ここでも大きなタイムロスが発生します。
2-2. 構造的な情報の属人化
建設業において営業負担を増大させる最も深刻な要因の一つが、情報の属人化です。
- 担当者の「頭の中」にある情報: 顧客との関係性、過去の経緯、微妙なニュアンスを含む交渉の記録、現場でしか知りえない情報などが、特定の営業担当者の記憶や個人的なノートの中に留まってしまいます。
- 非効率な情報検索: 担当者が不在もしくは退職した場合、その案件に関する情報をゼロから探し直す必要が生じます。これにより、顧客への対応が遅れたり、最悪の場合は過去の約束を反故にしてしまい信頼を失うリスクさえあります。
- 見積もり精度の低下: 積算に必要な最新の資材価格や現場での工数実績データが、積算担当者や現場監督個人の経験に依存していると、営業担当者が顧客に提供できる概算見積もりの精度が低くなります。これは、機会損失や後のトラブルの原因になります。
2-3. 相見積もり対応の泥沼化
第1章でも触れた相見積もり対応は、営業担当者のモチベーションとリソースを最も消耗させる活動です。その背景には、依頼主の評価基準の曖昧さが関わっています。
依頼主が、技術力、施工品質、アフターサービス、提案の創造性といった多面的な価値ではなく、単純な「価格」のみを比較の基準としがちな場合、企業努力は価格の引き下げに集中せざるを得ません。
- 非生産的な見積もり作業: 受注の確度が低いにもかかわらず、競合他社に負けないよう詳細で正確な見積もりを作成するために、膨大な時間を費やさなければなりません。この労力は、結果的に「無料の設計・積算サービス」を提供していることになりかねません。
- 精神的な疲弊: 丹精込めて作成した技術提案よりも、競合の安価な価格が優先された場合、営業担当者は自社の技術や努力が正当に評価されていないと感じ、大きな精神的疲労を負います。
営業負担を軽減するためには、まずこの「重労働」を構造的に生み出しているアナログなプロセス、情報の属人化、そして過度な価格競争への対応といった根本的な要因を理解し、次のステップであるデジタル変革と戦略的活用へと繋げていく必要があります。
3. デジタル活用による「営業の自動化・効率化」
3-1. 「待ち」の営業への転換:マッチングサイトの戦略的活用
第2章で確認した「追いかける営業」の重労働から解放されるための最も効果的な手段は、「発注ニーズが顕在化した顧客」に「選んでもらう」、つまり「待ち」の営業への転換です。この転換の核となるのが、建設専門マッチングサイト「ミツマド」のようなプラットフォームの戦略的な利用です。
ミツマドは、発注者と受注者を繋ぐ専門サイトであり、登録情報をもとに条件に合う案件を受発注することができます。
- 高確度案件の獲得: サイトに登録される案件は、すでに発注予算やプロジェクトの概要が明確なものが大半です。テレアポや飛び込みでゼロからニーズを掘り起こす必要がなく、受注確度の高い案件にのみリソースを集中できます。
- 移動コストのゼロ化: 案件情報はオンラインで閲覧し、コンタクトはメッセージで完結できます。これにより、無駄な訪問や移動時間が大幅に削減され、空いた時間を別の業務に割り振ることができます。
- プロフィール活用: ミツマドでは、会社情報に加えて施工事例なども掲載可能なため、自社のHP代わりに使うことが可能です。写真、工期、使用技術などを詳細に記載することで、発注者は自社のニーズに合っているかを事前に判断できます。
- 明確な強みの打ち出し: 「○○工事に特化」「特定の耐震技術に強み」など、専門性を明確に打ち出すことで、価格ではなく技術力で選ばれる土壌を構築できます。
3-2. テクノロジー導入による業務効率化
マッチングサイトによる「案件獲得の効率化」と並行して、社内の営業プロセスをデジタル化することで、さらに負担を軽減できます。
|
カテゴリー |
導入効果と軽減される負担 |
導入時のポイント |
|
SFA/CRM (営業支援・顧客管理) |
情報の属人化を完全に解消。 顧客との過去のやり取りや進捗状況、提出資料を一元管理し、担当者間の情報共有・引継ぎにかかる時間をゼロに近づける。 |
まずは「顧客とのコミュニケーションの履歴」と「進捗ステータス」の二点から入力をはじめる。ルールを最小限に設定することで、社内の定着を優先する。 |
|
クラウド型積算・見積もりソフト |
過去の実績データや最新の資材価格変動に基づき、正確な「概算見積もり」を数分で作成可能にする。 |
現場と連携し、完了した案件の工数実績データを確実にシステムに取り込むことで、見積もり精度を高めることができる。 |
|
電子契約・電子署名システム |
契約書の印刷、製本、郵送、捺印、保管という一連の作業を不要にし、契約締結までのリードタイムを数週間から数日へ短縮する。 |
弁護士などの専門家と相談の上、法律上の有効性を確認してから導入する。 |
|
オンライン連携ツール |
現場担当者との技術的な確認や、設計担当者との打ち合わせをビデオ会議で実施。また、緊急性に合わせてチャット機能も活用することで、業務効率を上げる。 |
社内ルールとして「緊急性の判断基準」を明確にし、電話とチャットの使い分けを徹底する。 |
3-3. デジタル活用で変革する「相見積もり」への対応
デジタルツールを駆使することで、相見積もり対応による疲弊も軽減できます。
- 「ワンクリック見積もり」の実現: クラウド積算ソフトの導入により、発注者が求める概算レベルの見積もりであれば、短時間で複数のパターンを提示できるようになります。これにより、「契約に至らない無駄な見積もり作成時間」を最小限に抑えます。
- プレゼンテーションの強化: 現場のBIM* /CADデータやドローンによる現場写真などのデジタルデータを活用することで、提案内容を視覚的に分かりやすくし、価格だけでなく技術や品質で差別化を図りやすくなります。
デジタル化は、単なる業務効率化ではなく、営業担当者を高度な提案活動に集中させるための戦略的な投資です。次の章では、この時間を使って、どのように営業体制そのものを強化するかを解説します。
*1:Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称です。コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデル(BIMモデル)を再現して、よりよい建物づくりに活用していく仕組みです。
【引用元】大塚商会「BIMナビ」
4. 属人化からの脱却と営業体制の再構築
4-1. 営業の職人技を組織の資産へ:標準化とマニュアル化
建設業の営業は、長年の実績と人とのつながりを背景にした熟練の技と捉えられることが多いです。しかし、この属人化こそが、営業担当者の負担を増大させ、欠員時のリスクを極限まで高めています。負担を軽減し、安定した受注を実現するためには、個人のノウハウを組織の資産に変える標準化が不可欠です。
- 共通ヒアリングシートの徹底:
- 初回コンタクト時に必ず確認すべき項目(予算感、希望工期、意思決定者、技術的な要求、見積依頼の状況など)を網羅した共通シートを作成し、全担当者に使用を義務付けます。
- これにより、顧客からの情報不足による手戻りや再確認の連絡を防ぎ、正確な見積もり作成までのプロセスを短縮できます。
- 提案書テンプレートの整備:
- 案件のタイプ(例:商業施設、住宅リフォーム、耐震改修)ごとに、基本構造と主要な訴求ポイントを盛り込んだ提案書のテンプレートを用意します。
- 営業担当者は、ゼロから資料を作成する膨大な時間から解放され、テンプレートのカスタマイズ(顧客固有の課題解決策を練る)という、より付加価値の高い作業に集中できるようになります。
- 情報共有ルールとSFA/CRMの活用:
- 第3章で触れたSFA/CRMを基盤とし、「顧客に接触したら即時入力」「提案資料は必ずクラウドに保存」といったシンプルなルールを徹底します。これにより、担当者が変わってもスムーズな引継ぎが可能となり、顧客への信頼低下を防ぎます。
4-2. 「現場力」を最大の営業資産に変える連携強化
建設業において最も強力な営業ツールは、他社には真似できない良い施工実績、すなわち「現場力」です。営業と現場が連携することで、営業担当者は質の高い根拠を持って提案できるようになり、結果として競争力を高め、価格競争からの脱却を助けます。
- 実績データベースの構築と活用:
- 工事完了後、現場担当者は必ずBefore/After写真、使用した特殊技術、顧客の声(アンケート)、実際にかかった工数などをデータベース化します。
- 営業担当者は、このデータを「ミツマド」の施工事例のページや、新規顧客への具体的な提案の根拠として即座に利用できるようにします。
- 「キーパーソン同行」のルール化:
- 技術的な専門性が高い重要な案件では、初回から現場監督や設計担当者が営業に同行することをルール化します。
- これにより、発注者の専門的な質問に対し、その場で正確かつ説得力のある回答を提供でき、営業担当者が情報を持ち帰って確認する手間(伝書鳩の役割)が不要になります。この即応性が、発注者の信頼感と安心感を劇的に高めます。
4-3. 営業担当者の役割再定義:マネジメントと創造性の強化
営業負担の軽減は、単に作業を減らすことではありません。低付加価値な作業(移動、事務処理、情報検索)から解放された時間を、高付加価値な活動へ振り向けることです。
- マネジメントへのシフト: 担当者は、現場の進行状況や顧客のニーズを俯瞰し、プロジェクト全体をコーディネートするマネージャーとしての役割を強化します。
- 創造的な提案活動: 削減された時間を使い、顧客の潜在的な課題を深く掘り下げ、競合他社にはない、一歩踏み込んだ創造的なソリューション(省エネ提案、新素材の活用など)を練り上げる時間に充てます。
営業の標準化と現場との連携により、属人化を排除し、組織全体の営業力を高めることが、持続的な負担軽減と受注拡大の鍵となります。
5. 軽減された負担の先にある、建設業の未来像
5-1. 持続可能な成長のための投資
これまでの章で解説してきたデジタル化と営業体制の再構築が実現したとき、建設業の営業担当者、ひいては企業全体に大きな変化が訪れます。営業担当者は、もはや重労働の渦中にいるのではなく、戦略家としての役割を全うできるようになります。
負担軽減によって生まれた時間は、企業にとって最も重要な成長領域に振り向けられます。
- コア業務への集中: 移動や事務処理に費やされていた時間が、現場の安全管理、施工品質のチェック、高度な技術の研鑽といった、企業の競争力の根幹に関わる業務に充てられます。
- 人材育成とスキルアップ: 営業担当者は、空いた時間を利用して、BIM/CIM*2 などの新技術や、ファシリテーション(会議の進行)スキルといった高度な知識・技術を習得できます。これは、企業の技術力を底上げし、将来的な難易度の高い案件への対応力を高めます。
- リスク管理の強化: 余裕が生まれることで、契約前のリスク分析や法的なチェックをより慎重に行うことが可能となり、プロジェクト途中のトラブルやクレーム発生のリスクを未然に防ぎます。
*2:計画、調査、設計段階から3 次元モデルを導入することにより、その後の施工、維持管理の各段階においても3 次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る取り組みです。
【引用元】大塚商会 CAD Japan.com「BIM/CIMとは - 目的や効果、原則適用について解説」
5-2. 「価格競争」から「価値創造」へ:選ばれる企業になるために
営業負担の軽減は、単に楽になるという福利厚生的な話に留まりません。それは、企業が市場での立ち位置を、価格で選ばれる企業から「価値と信頼で選ばれる企業」へとシフトさせるための、経営戦略そのものです。
マッチングサイト「ミツマド」のようなプラットフォームで、自社の技術力や実績を手間なく、かつ効果的に発信し続けることができるようになれば、自ずと発注者からの評価は、価格から実績や提案力へと移行します。
そして、企業は利益率の低い相見積もり対応から解放され、高い付加価値を提供でき、収益性の高い案件に集中できるようになります。これは、社員の満足度向上や企業の財務体質強化、そして何よりも建設業の未来への確かな投資となります。
6. 今すぐ始めるべき「営業負担軽減」のためのアクションリスト
建設業の未来は、営業のあり方にかかっています。今日から実行できる具体的な3つのステップをまとめました。
6-1. アクションリスト(実行計画)
|
ステップ |
実行内容と目標 |
期限(目安) |
|
ステップ 1:デジタルシフトの第一歩 |
建設専門マッチングサイト「ミツマド」への登録と、企業プロフィール、施工実績の充実化。 目標: 2週間以内に「待ちの営業」の基盤を構築する。 |
2週間 |
|
ステップ 2:属人化の解消 |
ヒアリングシートと基本的な提案書のテンプレートを作成。 目標: 見積もり依頼を受けてから提案書提出までの時間を20%削減する。 |
1ヶ月 |
|
ステップ 3:現場との連携強化 |
完了した工事の実績データ(写真・工期・顧客の声)をクラウド(SFA/CRM)に集約するルールを確立。 目標: いつでも使える営業資料として活用できるようにする。 |
2ヶ月 |
この変革は、一人の営業担当者の努力に委ねるものではなく、経営層が主導し、現場と営業が一体となって取り組むべき組織的な挑戦です。
負担を減らし、本来の使命である「社会基盤の創造」に集中できる、持続可能な建設業の実現に向けて、今日から一歩踏み出しましょう。
営業活動の負担を減らしたい…という方には、建設業専門のマッチングサイト「ミツマド」がおすすめです。50工種以上の幅広い案件を受発注することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。