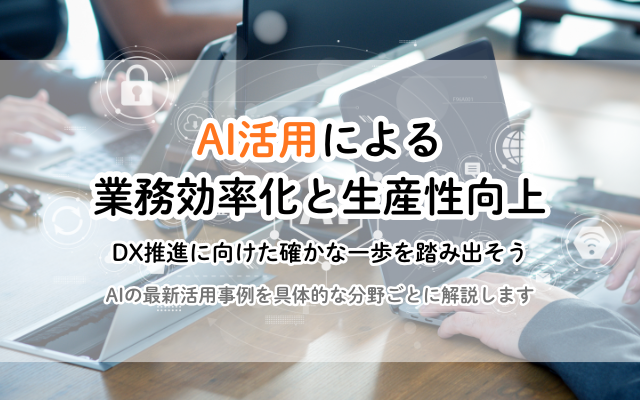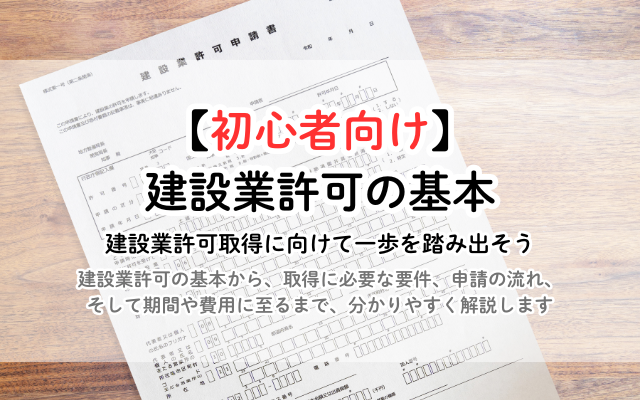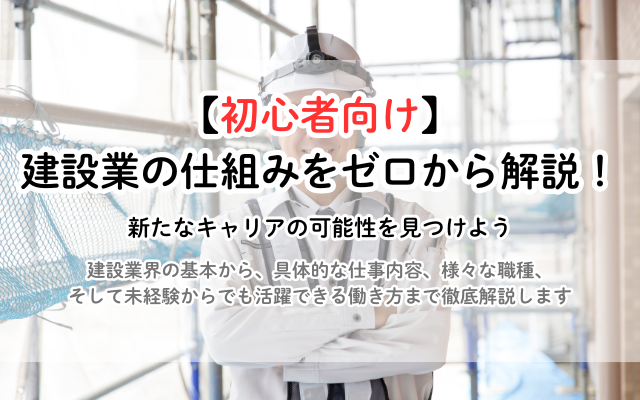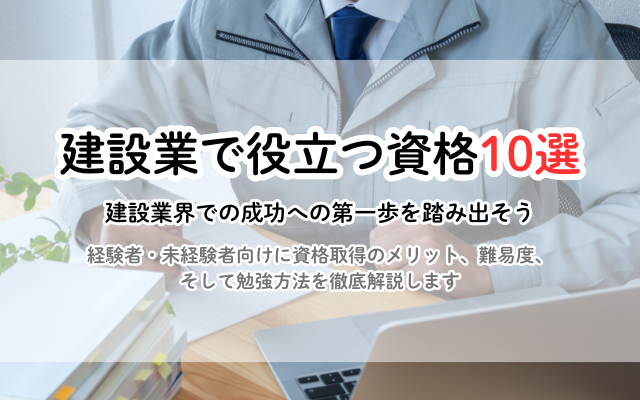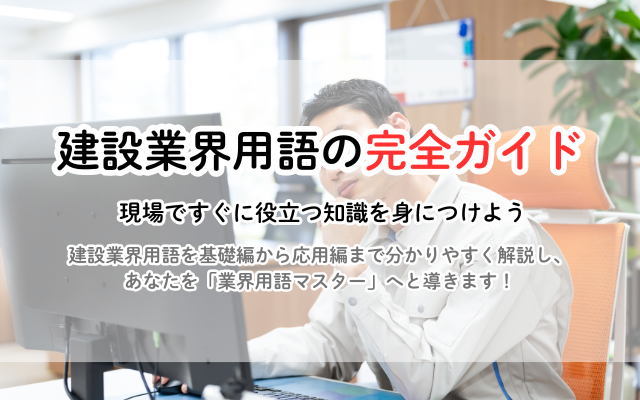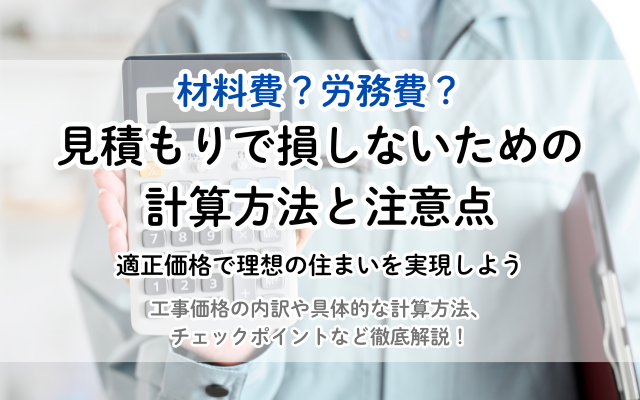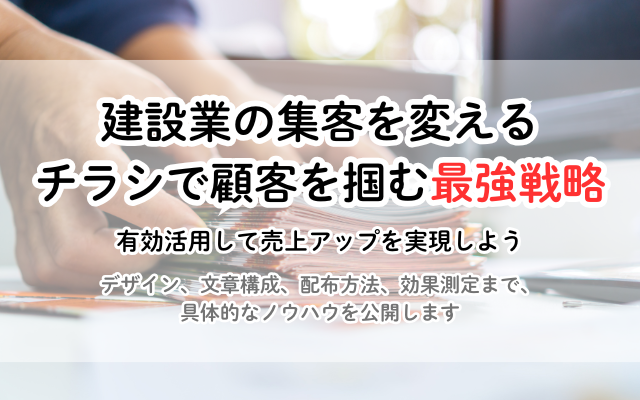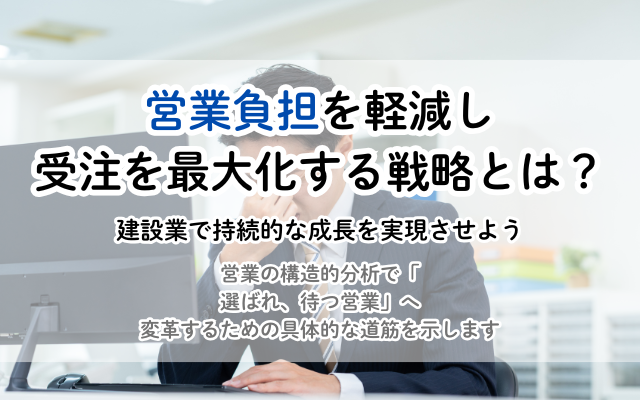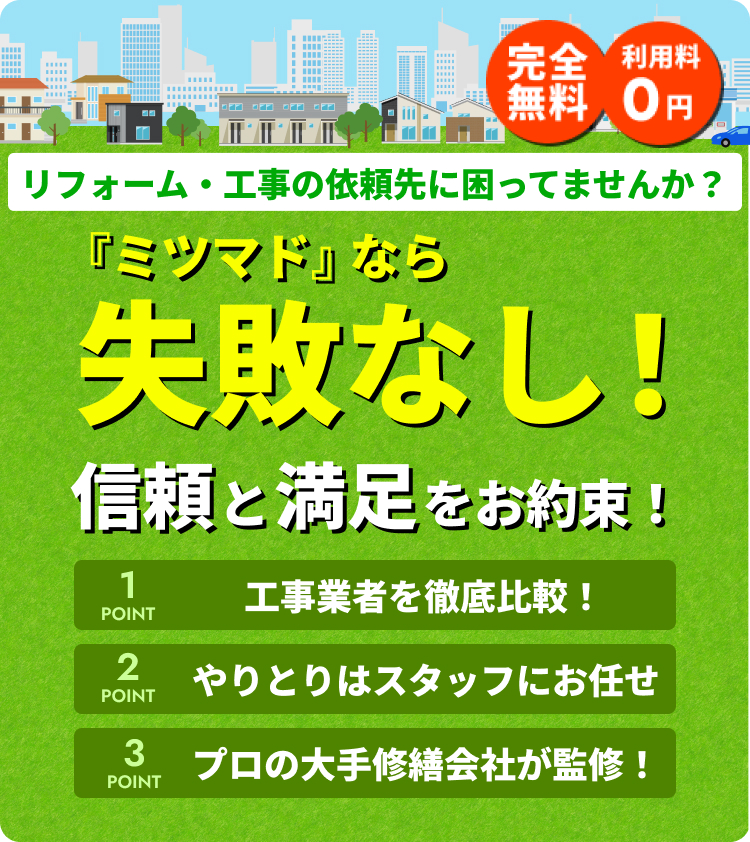1. 2025年建設業法改正の全体像
建設業法の改正は、労働者の処遇改善、資材価格高騰への対応、そして働き方改革といった、業界が直面する喫緊の課題に対処し、持続可能な発展を目指すものです。建設業に携わるすべての人々がこの変化に対応し、新たな時代を乗り越えるための基盤となる情報を提供します。
1-1. 改正の背景と目的
建設業法改正は、近年の社会経済状況の変化、特に人手不足の深刻化、資材価格の不安定化、そして若年層の入職者減少といった構造的な問題を背景としています。これらの課題に対応するため、法改正では、建設労働者の賃金や労働条件の改善を促進し、魅力ある業界へと転換を図ることが目的とされています。また、資材高騰に対する価格転嫁の円滑化や、生産性向上に資する技術導入の推進、さらには柔軟な働き方を可能にする制度整備なども、政府が目指す主要な目的として挙げられます。これにより、業界全体の競争力強化と、より良い労働環境の実現を目指します。
1-2. 施行スケジュール
2025年に施行される建設業法改正は、一度にすべてが実施されるのではなく、段階的に導入される見込みです。主要な改正内容は、法律の公布から一定期間を経て、順次施行されていくことになります。具体的な施行時期については、各条項や改正内容によって異なりますが、最新の情報を注視し、自社の事業計画への影響を早期に把握することが求められます。施行スケジュールを理解することは、改正への円滑な対応と新たな制度を最大限に活用するための第一歩となります。
2.主な改正ポイント
建設業を取り巻く環境は、労働者の処遇改善、資材価格の高騰、そして働き方改革といった喫緊の課題への対応を迫られる中、法改正によって大きく変化しています。特に2025年に施行される改正は、これらの重要課題に直接関わるため、その内容を正確に理解することが不可欠です。本セクションでは、具体的な例を交えながら、主な改正ポイントを分かりやすく解説します。
2-1. 賃金水準の確保
建設業における人手不足と高齢化は深刻な問題であり、魅力ある産業として次世代を担う人材を確保するためには、労働者の賃金水準の向上が急務です。今回の法改正では、建設労働者の賃金底上げを促進するための具体的な制度や、企業が遵守すべき要求事項が定められています。
これにより、より適正な価格での請負や生産性向上への投資が促され、結果として賃金に還元される仕組みが期待されています。例えば、最低賃金制度の見直しや業界団体による賃金ガイドラインの策定などが考えられており、建設業の社会的地位向上と労働者の生活の質の向上が目指されます。
2-2. 労働条件の改善
建設現場の過酷な労働環境は、離職率の高さや健康問題の一因となってきました。法改正では、長時間労働の是正や休暇取得の促進、安全衛生管理の強化など、労働条件全般の改善に向けた具体的な措置が盛り込まれています。例えば、法定労働時間を超える残業に対する罰則の強化や、現場作業員への年次有給休暇取得奨励策、さらには、より安全な作業環境を整備するための最新技術の導入支援などが挙げられます。
これらの取り組みは、建設労働者が健康で安心して働ける環境を整備し、持続可能な産業基盤を構築するために不可欠です。
2-3. リスク情報の提供義務
工事の請負契約においては、発注者と受注者の間で情報格差が生じやすく、これが予期せぬトラブルや追加コストの原因となることがあります。今回の改正では、発注者に対し、工事に関する潜在的なリスク情報(例:地盤の状況、埋設物の有無、過去の類似工事での問題点など)を受注者に事前に提供する義務が課されました。
この情報提供により、受注者はより正確な見積もりを作成でき、工事計画を適切に立案することが可能になります。結果として、契約内容の不明確さから生じる紛争を未然に防ぎ、円滑な工事の遂行に繋がります。
2-4. 請負代金変更方法の明確化
資材価格の急激な変動は、建設プロジェクトの採算性に大きな影響を与えます。これまで、価格変動への対応は契約当事者間の協議に委ねられる部分が大きく、その手続きが不明確であることが問題視されていました。改正法では、請負代金の変更手続き、特に資材価格の変動があった場合の協議方法や変更額の算定基準などが、より明確に規定されました。
これにより、予見できない経済情勢の変化に対しても、契約当事者双方が公平かつ迅速に対応できるようになり、プロジェクトの安定的な遂行を支援します。
2-5. 変更協議への誠実な対応
建設工事においては、予期せぬ事態の発生や計画の変更に伴い、契約内容の見直しが必要となる場面が少なくありません。法改正では、契約内容の変更に関する協議において、発注者および受注者の双方が「誠実に対応する義務」を負うことが明記されました。これは、一方的な要求や不誠実な対応によって協議が遅延・決裂することを防ぎ、両当事者が協力して最善の解決策を見出すことを促すものです。
この原則の徹底は、建設プロジェクトにおける信頼関係を強化し、円滑な事業遂行の基盤となります。
2-6. 著しく短い工期の禁止
建設プロジェクトの成功には、適切な工期の確保が不可欠です。しかし、過去には、発注者側の都合により現実的に達成不可能なほど短い工期が設定され、それが過重労働や品質低下、安全性の問題を引き起こすケースがありました。改正法では、「著しく短い工期の禁止」が明確に規定され、工事の規模や内容、性質を考慮し、合理的な期間を設定することを義務付けられました。
これにより、無理なスケジュールによるリスクを排除し、安全かつ質の高い建設工事の実現を目指します。
2-7. 現場技術者の専任義務合理化
建設現場においては、専門知識を持った技術者の配置が、工事の品質や安全を確保する上で極めて重要です。従来、特定の規模以上の工事では、技術者は原則としてその現場に専任で配置される義務がありました。しかし、今回の改正では、技術者の配置に関する専任義務が合理化されます。例えば、技術者の能力や経験、工事の規模や複雑性などを考慮し、一定の条件下においては、複数の現場を兼任することが可能になる場合があります。
これにより、限られた技術者のリソースをより効率的に活用し、中小企業などでの人材不足の緩和に貢献することが期待されます。
2-8. ICT活用による現場管理の推進
建設業界の生産性向上と効率化は、長年の課題であり、その解決策としてICT(情報通信技術)の活用がますます重要視されています。法改正は、建設現場におけるICTの導入と活用を積極的に推進する方向性を示しています。具体的には、BIM(Building Information Modeling)*1 の活用、ドローンによる測量・進捗管理、IoTセンサーによる設備監視、クラウドベースのプロジェクト管理システム導入などが挙げられます。
これらの技術は、設計段階での精緻なシミュレーション、施工精度の向上、リアルタイムでの情報共有、データに基づいた意思決定を可能にし、建設プロジェクト全体の生産性向上、コスト削減、品質向上、さらには安全性の向上に大きく貢献します。
*1:Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称です。コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデル(BIMモデル)を再現して、よりよい建物づくりに活用していく仕組みです。
【引用元】大塚商会「BIMナビ」

3. 企業が取るべき対策
2025年に施行される建設業法改正は、建設業界の企業経営に大きな影響を与える重要な転換点となります。本セクションでは、この法改正に対応するために企業が取るべき具体的な対策を、段階を追って詳しく解説します。
3-1. 情報収集と理解
法改正への対応は、まず正確な情報収集から始まります。国土交通省より発表される最新情報はもちろん、業界団体が提供する解説資料やセミナーなどを活用し、改正のポイントを深く理解することが不可欠です。自社への具体的な影響を把握するためには、法改正の条文だけでなく、施行令やガイドラインなども参照し、多角的に分析する必要があります。収集した情報は、経営層から現場担当者まで関係者全員で共有し、共通認識を持つための社内勉強会などを実施することも有効です。これにより、改正内容に対する誤解を防ぎ、統一された対応を可能にします。
3-2. 労務管理の見直し
建設業法改正は、労働者の権利保護や労働環境の改善を強化する側面も持ち合わせています。これに対応するため、企業はまず自社の労務管理体制を徹底的に見直す必要があります。具体的には、最低賃金や法定福利費の引き上げに対応できる給与体系の見直し、残業時間の上限規制遵守のための勤務体制の再構築、そして、年次有給休暇の取得促進や、育児・介護休業制度の拡充といった福利厚生の整備が求められます。就業規則についても、これらの変更点を反映させ、従業員への周知を確実に行うことが重要です。これにより、法令遵守はもちろん、優秀な人材の確保・定着にも繋がります。
3-3. 契約の見直し
法改正は、建設工事の請負契約における取引の適正化も目的としています。そのため、既存の契約書や発注者・受注者間の取引慣行を見直し、改正内容に適合させる必要があります。特に、請負代金の算定方法、変更協議のプロセス、そして工期の設定に関する条項は、注意深く確認すべき点です。不当に短い工期設定の禁止や、設計変更時の追加費用・期間の適切な取り扱いなど、契約書に明記することで後々のトラブルを防ぎ、公正な取引を実現することが可能になります。発注者との間で、改正の趣旨を理解し、双方にとって納得のいく契約内容を構築することが求められます。
4. 建設業法改正に関するQ&A
建設業法改正の施行が目前に迫り、建設業界全体でその影響や具体的な対応について関心が高まっています。多くの事業者様から、日々の業務や経営にどのように関わるのか、具体的な疑問や不安の声が寄せられています。本セクションでは、こうした皆様の疑問を解消し、改正への理解を深めていただくために、よくある質問とその回答をQ&A形式で分かりやすく解説していきます。
Q: 建設業法改正はいつから施行されますか?
法改正の内容によって施行時期は異なりますが、多くの主要な改正点は2025年12月より施行される予定です。詳細な施行スケジュールについては、国土交通省の発表をご確認ください。
Q: 今回の法改正で、最も影響が大きいと思われる点は何ですか?
今回の改正では、特に「建設工事の適正な請負代金の額の算定」や「建設業者の技術力・経営力向上の促進」、「持続可能な建設工事の実施」などが重点項目となっています。例えば、下請取引における適正な工期設定や、資材価格の変動への対応などがより厳格に求められるようになるでしょう。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)*2 の推進や、働き方改革への対応も、今後の建設業経営において不可欠な要素となります。
*2:IT技術やビッグデータなどデジタル技術を駆使して、業務プロセスや事業内容を改革することを意味します。
【引用元】一般社団法人 日本ディープラーニング協会「DXとは?意味や推進のための5つの段階をわかりやすく解説」
Q: 中小規模の建設業者でも対応が必要ですか?
規模の大小にかかわらず、すべての建設業者が改正内容を理解し、必要な対応を行う必要があります。特に、請負代金の算定基準の明確化や安全管理体制の強化などは、事業継続のために重要です。必要に応じて、専門家のアドバイスを受けたり、業界団体が提供する研修に参加したりすることをお勧めします。
Q: 経営事項審査(経審)に何か変更はありますか?
経営事項審査においても、技術力や経営状況の評価基準が見直される可能性があります。例えば、若手技術者の育成や社会保険加入状況の評価が強化されるといった変更が考えられます。これにより、より実態に即した企業の評価が行われるようになるでしょう。最新の審査基準については、国土交通省の発表や関連機関からの情報にご注意ください。
Q: 法改正に対応しない場合、どのようなリスクがありますか?
法改正の趣旨に沿わない経営や取引を行った場合、行政指導や監督処分の対象となる可能性があります。また、取引先からの信頼を失ったり、競争力が低下したりするリスクも考えられます。建設業法は、建設業の健全な発展と公共の福祉の増進を目的としており、その遵守は事業者の義務です。
5. まとめ
本記事では、その改正の全体像から具体的なポイント、そして企業が取るべき対策までを詳細に解説してきました。
今回の建設業法改正は、建設業許可制度の見直し、請負契約の適正化、技術者の育成・確保といった多岐にわたる項目を含んでいます。これらの変更は、業界全体の透明性向上、労働環境の改善、そして生産性向上を目指すものです。
企業がこの改正に適切に対応するためには、まず最新の法規制を正確に理解し、自社の業務プロセスとの整合性を確認することが不可欠です。具体的には、社内規程の見直し、従業員への教育実施、ITツールの導入による業務効率化などが求められます。特に、建設キャリアアップシステム*3 への対応や、若手人材の育成・定着に向けた取り組みは、中長期的な競争力強化に繋がるでしょう。
法改正は、建設業界が直面する課題を克服し、持続可能な成長を遂げるための重要な転換点となります。この機会を捉え、技術革新、働き方改革、DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進することで、業界全体の魅力と生産性を一層高めていくことが期待されます。変化を恐れず前向きに対応していくことが、企業のさらなる発展と、より良い社会基盤の構築に貢献するものと確信しています。
*3:技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
【引用元】建設キャリアアップシステム「CCUSについて」
案件の受発注をシステムで一元化したい…という方には、建設業専門のマッチングサイト「ミツマド」がおすすめです。50工種以上の幅広い案件を受発注することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。